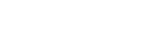リーダーシップ研修
目次
- リーダーシップ研修とは
- 研修の狙い
- プログラム
- リーダーシップとは
- リーダーシップ研修の目的
- リーダーシップ研修の対象者と研修内容
- リーダーシップ研修を効果的に行うポイント
- リーダーシップ論の変遷
- コンセプト理論での代表的なリーダーシップスタイル
人を巻き込み影響を与えるリーダーシップを習得する
リーダーシップ研修とは
リーダーシップ研修とは、職務上リーダーシップが求められる人材に対し、リーダーとしての知識や能力を身につけてもらうための研修です。
研修の狙い
- リーダーシップの基礎を学ぶ
- 様々なリーダーシップスタイルから状況に応じたリーダーシップを発揮する
- リーダーとして部下をやる気にさせるスキルを身につける
プログラム
※内容は、貴社のご要望に応じ、カスタマイズが可能です。
※時間の目安は10:00~17:00です。
1.リーダーシップとは何か
(1)リーダーシップとは【グループワーク】
(2)リーダーとリーダーシップの違いとは
2.リーダーシップを発揮する要素
(1)リーダーシップに必要な影響力
(2)チームのビジョン・目標を持つ
(3)メンバーのモチベーションをマネジメントする
(4)メンバーとのコミュニケーション
3.マネジメントとリーダーシップは何が違うのか
(1)今と未来
(2)ポジションパワーとパーソナルパワー
(3)部下との関わり方
4.様々なリーダーシップスタイル
(1)目標達成と集団維持のリーダーシップ
(2)状況対応型のリーダーシップ
(3)サーバントリーダーシップ
(4)あなたのリーダーシップスタイルは?
5.リーダーとして部下にやる気を起こさせるコミュニケーション
(1)部下の欲求は何?
(2)積極的傾聴
(3)やる気を引き出す効果的な質問
(4)承認する
(5)内発的動機づけと外発的動機づけ
(6)褒める&叱るを活用する
6.まとめ
リーダーシップとは
リーダーシップとは集団をまとめ、その目的に向かって導いていく機能のことです。
後ほど詳しくご説明しますが、リーダーシップについては、定義や種類が多岐にわたりますので、自社の抱える課題や状況に応じてどのようなリーダーシップが有効であるのか、あるいは、自分自身にあったリーダーシップはどのようなものなのかを掘り下げて頂けたらと思います。
リーダーシップ研修の目的
リーダーシップ研修の目的は、大きくは次の二つです。
❶組織の目標達成や生産性向上
研修でリーダーとしての役割の認識やリーダーシップの能力を身につけることにより、組織や企業の目標達成と生産性向上を目指します。
❷組織の維持と活性化
リーダーとして、一人ひとりと向き合い、コミュニケーションを積み重ねることで、メンバーとの信頼関係を強固にし、組織全体を活性化させるます。
リーダーシップ研修の対象者と研修内容
リーダーシップ研修の対象者は、大きくは「中堅社員」「管理職」「次世代リーダー」の三つの階層が中心となります。
(1)中堅社員
当社では、入社5年目から管理職になる前までを中堅社員として考えています。その為、係長や主任(リーダー)を中堅社員として位置づけていますが、中堅社員に対しリーダーシップ研修を開催する企業は増えています。
小さな組織であっても、リーダーシップを発揮してもらいたいという、企業側の期待が強くなってきていることの表れであると考えられます。又、研修を通して管理職としての適性を判断する機会としても利用できます。研修で取り組むべき代表的なテーマを4つ挙げておきます。
❶プレイングマネージャーとしてマネジメント
❷上長と部下を巻き込むスキル
❸上司フォロー
❹ファシリテーションスキル
(2)管理職
もっとも企業ニーズの多い研修の対象が、新たに管理職として登用された、新任管理職です。
また既に管理職になった人に対しても、一層のスキル向上のために、実施されることもあります。研修で取り組むべき代表的なテーマを3つ挙げておきます。
❶リーダーとして必要なコミュニケーション能力
❷コーチングとモチベーションアップのためのスキル
❸業務推進に必要な問題解決・意思決定手法
(3)次世代リーダー
次世代リーダーとは、企業経営を担う重要なポジションへの就任を想定された人材のことを指します。
近年では、次世代リーダーを中堅社員の中から選抜し、リーダーシップ研修を受けさせるなど、早期発掘・育成のための取り組みを行う企業が増加しています。
自社の経営を受け継ぐ人材として育成することは企業の持続成長にとって必要不可欠ですので、社長自らが研修を行い、経営理念を継承している企業もあります。
以下に研修で取り組むべき代表的なテーマを2つ挙げておきます。
❶経営幹部としての意識の醸成
❷戦略策定、計画立案などの経営に関するスキルを学ぶ
リーダーシップ研修を効果的に行うポイント
リーダーシップ研修を効果的に行うポイントは以下の4点です。
(1)解決すべき課題と研修の目的を明確にする
リーダーシップを強化すべき組織課題は企業によって異なります。まずは自社の課題を把握し、研修の目的を明確にすることで、方向性を定めます。具体的には、対象とする階層を決め、目的を設定し、研修の方向性を定めましょう。
(2)研修内容を決める
研修修了後に「どのような状態になって欲しいのか」を決め、必要な研修内容を決めていきます。研修の効果を高めるためには、自社が抱える組織課題が複数ある場合は、優先順位をつけたうえで研修内容を決定することが必要です。
又、研修の実施に当たっては、企業側の期待する研修終了後の姿を明快に伝えることで、受講者は研修をなぜ受けているのか適切に理解し、効果は高まります。
(3)研修形態
研修形態には、社内研修や社外研修、オンライン研修などがあります。又、講師を社内から選ぶのか、外部に委託するかなど、研修の目的や内容によって、効果的なものを選択します。
(4)フォローアップの実施
研修実施後、参加者には、今後の実施計画を立ててもらうことが重要です。研修を実施すれば知識や能力が身につくわけではありません。
研修で得た気付きを実践の場で活かすことこそが、リーダーシップを身に付ける近道であり、同時に、その状況をフィードバックするフォローアップ体制の構築を心がけましょう。
リーダーシップ論の変遷
リーダーシップ論に関する研究は古代ギリシャまで遡ると言われていますが、現代的リーダーシップ論の研究は、19世紀イギリス(大英帝国)の歴史家・評論家トーマス・カーライルが歴史的な「偉人」を採り上げて、「他より優れた何らかの資質を持ち合わせた偉人だけがリーダーと成り得る」と提示したのが始まりと言われています。
その後、1900年代になるとアメリカなどを中心にその理論化・体系化が進められてきました。
これまで、研究されてきた主なリーダーシップ論は下記の4つが代表的です。
(1)特性理論( 1900 年代~)
「リーダーシップは先天的な性質で生まれ持った者である」という前提のもとに、優れたリーダーに共通する特性を特定しようと試みられました。
(2)行動理論( 1940 年代~ 1960 年代)
「行動理論」は、リーダーの行動に着目して、共通の特徴を抽出しようとしたものです。代表的な理論に三隅二不二が提唱したPM理論があります。
「P」:「目標達成・課題解決機能」(Performance)
「M」:「集団維持機能」(Maintenance))
⇒共に高いことが理想のリーダーである
(3)条件適合型理論( 1960 年代後半~)
「行動理論」に関する実証研究の結果から、あるチームで優秀なリーダーであっても他のチームで優秀なリーダーであるとは限らないことが判明しました。
その結果、部下やビジネス市場、課題の困難さなどのリーダーを取り巻く環境でリーダーシップ行動を変化させるべきであるという「条件適合型理論」へと発展しました。
(4)コンセプト理論( 1970 年代~現在まで)
コンセプト理論は、前身となる「条件適合理論」を継承した理論です。コンセプト理論は、「条件適合型理論」を前提としながら、さらにビジネス環境や組織・メンバーの状況に応じて、さまざまなパターンでのリーダーシップのとり方を具体的に落とし込んでいったもので、問題設定の際に「リーダー(人間)」と「リーダー(人間)をとりまく環境」の関係性に焦点を当てて議論を行っています。
コンセプト理論での代表的なリーダーシップスタイル
比較的新しいリーダーシップ論であるコンセプト理論では、状況の数だけ適したリーダーシップが存在することになり、リーダーシップ論のすべてを把握することが難しくなっています。代表的な5つのリーダーシップについてご説明しますので、自社の抱える課題や状況に応じてどのようなリーダーシップが有効であるのか、あるいは、自分自身にあったリーダーシップどのようなものなのかを掘り下げ頂けたらと思います。
(1)カリスマ型リーダーシップ
並外れた行動力と発想で、組織を力強く牽引するタイプのリーダーシップです。一般的にカリスマは、 先天的に人々の心を引きつけるような強い魅力または、それをもつ人を意味し、「カリスマ性のある人物」「ファッション界のカリスマ」というような使われ方をします。コンセプト理論における「カリスマ型リーダーシップ」は、1977年ハウス(R.House)によって、先天的な特性ではなく、「部下にカリスマと認知されることで、リーダーはカリスマとなりうる」「きわめて高水準の自己信頼と部下からの信頼があることで、リーダーは部下を目標に導くことが可能である」と再定義されました。更に部下からの認知、という視点から「具体的にどんな行動を取れば、リーダーはカリスマと認知されるのか」について、リーダーシップ研究者であるコンガー(J.Conger)、カヌンゴ(R.Kanungo)が研究を行い、カリスマ型リーダーの行動特性として、以下の6つの特徴を挙げています。
ⅰ)ビジョンの表明
フォロワーを鼓舞する戦略的・組織的目標を示し、効果的に表明し浸透させる
ⅱ)環境への感受性
組織を取り巻く環境やメンバーの能力について正しく認識する
ⅲ)型にとらわれない行動
常識や前例にとらわれない手段を用いる
ⅳ)リスクをいとわない
リーダー自らが責任を取る覚悟を持つ
ⅴ)メンバーのニーズに対する感受性
フォロワーと尊敬し合える関係を作りだし、ニーズや感情に敏感になる
ⅵ)現状の否定
現状に満足せず、常に変化と成長を求める
カリスマ型リーダーシップは、次にご説明する「変革型リーダーシップ」とともに、組織を変革するためのリーダーシップとして力を発揮し、組織を急成長させる原動力となる大きなメリットがある一方、リーダーの影響力が強すぎることで生じるリーダーへの依存や、後継者育成の問題などが生じる懸念を孕んでいます。代表的な人物にはAppleのスティーブ・ジョブズ氏、Microsoftのビル・ゲイツ氏、セブン&アイ・ホールディングスの鈴木敏文氏などが挙げられます。
(2)変革型リーダーシップ
「変革型リーダーシップ」とは、変革型リーダーシップ理論の代表的な学者である、ミシガン大学ビジネススクールのノール・M・ティシー教授が1986年に発表した「変革型リーダーシップ理論」から生まれた言葉です。
経営危機の会社のトップなどに求められるスタイルで経営方針を抜本的に見直し、メンバーに「自発的な行動」を促し大きな改革を推し進めるように働きかけるリーダーシップです。
【ティシーによる「現状変革型リーダー論」】
ティシー教授は、リーダーはビジョンを提示し、それを実行させるべくメンバーに働きかける存在であり、日常の反復業務やルール通りの管理に長けた「マネジャー」ではなく、変革を実行するとし、「リーダー」のあり方を明確に定義しました。また、リーダーが組織のあらゆる階層に存在し、リーダー自らが次世代のリーダーを生み出していく仕組みづくりが大切である、という「リーダーシップ・エンジン」という概念を主張しています。
①リーダーが行うべきこと
ⅰ)現状をあるがままに捉え、ステップを辿りながら変革を実行する
ⅱ)リーダー自身のアイデアと価値観によって他者を導き、動機付け、物事を達成する
ⅲ)3つの組織システムへ働きかける
・技術的システム(経営資源の組織化)
・政治的システム(従業員にやる気を起こさせるために権力、影響力、報酬をどのように使うか)
・文化的システム(従業員を結束させる規範と価値観)
②変革型リーダーの特徴
ⅰ)変革者と自らを任じている
ⅱ)勇気のある人たちである (リスクを取ることをいとわない)
ⅲ)人を信じる (人の気持ちに敏感で、人への動機づけに重きを置く)
ⅳ)価値によって動く
ⅴ)生涯にわたって学び続ける人である (失敗を将来への糧と考える)
ⅵ)複雑さ、あいまいさ、そして不確実性に対処する能力がある
ⅶ)ビジョンを追う人間である
③リーダーシップ・エンジン
ティシー教授は、組織の全階層で、人々がアイデア、価値観、エネルギーとエッジ(大胆な意思決定力)をもって、すばやくかつ適切に意思決定を下し、行動することが必要であると述べています。そのためには、リーダーが組織のあらゆる階層に存在し、彼ら自身が次代のリーダーを次々と生み出していく仕組みである「リーダーシップ・エンジン」こそが、組織が永続的に「勝ち」続けていく為に必要であると提唱しています。代表的な人物には、良品計画の松井忠三氏、日本マクドナルドホールディングスの原田泳幸氏、日本航空を再生させた稲盛和夫氏などが挙げられます。
(3)EQ型リーダーシップ
人間関係を重視し、職場環境の改善や部下のモチベーションの維持に細かく注意を払うリーダーシップで、組織内の人間関係やモチベーションなどの改善が問題となっている場合は効果的です。
【EQとは】
EQとは「Emotional Intelligence Quotient」の略で、直訳すると「感情的知能指数」となり、「心の知能指数」と呼ばれています。
心の知能指数とは、以下の能力のことです。
●自身の感情や他人の感情に気づけること
●感情を適切に分けられること
●自身の感情を認識し行動できること
IQ=知能指数(Intelligence Quotient)が高い人ほど、ビジネスで成功すると考えられがちですが、IQが高くてもビジネスで失敗している人が多くいるのが現実です。
一方、ビジネスで成功している人の共通点から導き出された成功の要因は、「ビジネスで成功している人は対人関係能力に優れている」というものでした。
20世紀末期にアメリカの心理学者、ダニエル・ゴールマン(Daniel Goleman)により提唱されたこのEQ型リーダーシップは、「部下の感情を正しく導くことで、組織運営を良い方向に導く」という考えに基づいています。
【EQ型リーダーシップのリーダーシップスタイル】
EQ型リーダーシップは、メンバーとのコミュニケーションが不可欠とされており、以下の4つのポイントを段階的にクリアしていくことは「人間関係を適切に管理する」という最終的なフェーズへ向かうためのステップであり、EQ型リーダーシップを適切に発揮できるポイントとされています。
ⅰ)自己認識:「自分の感情を読み取り正しく自分を評価できる能力」
ⅱ)自己管理:「自分の感情をコントロールし状況に柔軟に誠実に対応していく能力」
ⅲ)社会認識:「他者の気持ちを汲む能力」
ⅳ)人間関係の管理:「求心力と紛争処理と協調性の能力」
【6つのリーダーシップスタイル】
現代のリーダーシップ理論で重要なのは「リーダーシップは個人の資質だけでなく、他者や環境との関係性により変化する」という考え方です。EQを身に付ける事ができれば、感情をコントロールできるようになり、状況に応じてリーダーシップを使い分けることが可能になります。EQ型リーダーシップでは、状況に応じて以下の6つのリーダーシップを使い分けることが提唱されています。
①ビジョン型リーダーシップ
方向性を示すことで、部下の感情を良い方向へ導こうとするリーダーシップです。チーム全体で共通の目標を設定するなど、組織としてのコミットメントを生み出すことが特徴です。
②コーチ型リーダーシップ
部下の長所短所などを対話によって引き出し、自らの行動目標の設定をサポートするリーダーシップです。
③関係重視型リーダーシップ
業務目標の達成よりも、部下の承認や感情面のケアを重視したリーダーシップです。組織内のコミュニケーションを円滑にする狙いがあります。
④民主型リーダーシップ
メンバーとの対話やミーティングに時間を割き、組織としてどうしていくかの方向性を全体で決めるように舵をとるリーダーシップです。メンバー一人ひとりの考えを掘り起こし、組織で共有が必要な際に発揮されます。
⑤ペースセッター型リーダーシップ
リーダーが部下に高いレベルのパフォーマンスを求め、それを自らやってみせる「背中で語る」タイプのリーダーシップです。メンバー全員の能力が高く、モチベーションが高い時に有効です。
⑥強制型リーダーシップ
メンバーに対し、一方的に指示のみをするリーダーシップです。EQ型リーダーシップの代表的な人物には、積極的にあいさつする、声をかける、ほめる、認めるなどでメンバーの感情をポジティブな方向へリードしている元ダイエー会長 林文子氏が挙げられます。
(4)ファシリテーション型リーダーシップ
メンバーの自発的な行動を尊重し、業務意欲や成長を促すような行動をとるリーダーシップで、民主主義的な組織を作り、業務を通しての信頼関係構築を目指すスタイルです。
「部下と上司」という上下関係に基づくコミュニケーションではなく、同じ目線に立って部下の声を傾聴するのが特徴です。
ファシリテーション(facilitation)とは、楽にする、促進する、容易にするという意味のfacilitateから転じて、対立しがちで合意形成や相互理解が妨げられがちなチーム・組織などを効果的・効率的に運営することを指し、ファシリテーションを実践する人のことを「ファシリテーター」と言います。
『ファシリテーター型リーダー時代』の著者であるフラン・リース氏は、ファシリテーターの定義を「中立な立場で、チームのプロセスを管理し、チームワークを引き出し、そのチームの成果が最大となるように支援する人」としています。これに「チームメンバー全員を共通の目標に向かわせること」をつけ加えることで、一層ファシリテーション型リーダーの役割が明確になると思います。
ファシリテーション型リーダーシップにおいて重要なのは、リーダーによる意見の押し付けや指示命令を行うのではなく、自身は中立な立場で、メンバーを主体に意見や情報を引き出した上で、意見や結論をまとめ、メンバーに主体性をもって行動させるようにします。
その結果、メンバーのモチベーション向上にとても効果的であると言えます。一方、メンバーの意見の取りまとめができなければ、議論が堂々巡りとなるばかりか、意見の対立からメンバー同士の軋轢を生み出すことにつながる危険性も孕んでいます。
そのため、リーダーは適切なファシリテーションスキルを身につけるとともに、日頃からメンバーとの信頼関係を築き、相互に協力する人間関係を構築する必要があります。代表的な人物には、星野リゾートの星野 佳路氏が挙げられます。
(5)サーバントリーダーシップ
リーダーがメンバーの業務をサポートするリーダーシップです。リーダーが裏方の仕事を行い、メンバーに奉仕・サポートすることにより、メンバーは顧客業務などに集中し、顧客満足度を向上させビジネスを好循環させる狙いがあります。
もちろん、組織としての大きな決断の最終意思決定や責任はリーダーが行いますが、その上で、メンバーを上手くサポートすることで、メンバー一人ひとりが思い切った行動をとりやすくなるのが特徴です。
サーバントリーダーシップの提唱者は、元AT&T(米国の大手通信会社)マネジメントセンター所長のロバート・K・グリーンリーフ(1904-1990)です。グリーンリーフが、1970年に書いた『リーダーとしてのサーバント』という小論で、初めてサーバントリーダーシップという言葉が使われました。
サーバントリーダーシップの啓蒙拠点である「ロバート・K・グリーンリーフ・センター」の所長であったラリー・スピアーズが、サーバントリーダーの特徴である10属性を挙げています。
【スピアーズによる10属性】
①傾聴
傾聴することでメンバーの考えを引き出し、メンバーが能力を発揮できるサポートの方法を考える
②共感
相手の気持ちに共感し、相手が何をしてほしいのかを理解する
③癒し
欠けているもの、傷ついているところを探し出し補完することでメンバーに癒しを与え、パフォーマンスを引き出す
④気づき
メンバーが能力を発揮できるよう、チームはもちろん、他部門や組織全体をよく見て、そこから得た「気づき」をマネジメントに活かしていく
⑤説得
意見の相違が生じた際、職位によってメンバーを服従させるのではなく、話し合いによって説得する
⑥概念化
組織やチームが何を目指すのか、ビジョンを分かりやすく伝える
⑦先見力、予見力
現状や過去の事例から、将来の展望を予測する
⑧執事役
大切なことを任せられる信頼できる人となる
⑨人々の成長への関与
相手の可能性や価値に気付き、その成長を促す
⑩コミュニティづくり
メンバー一人ひとりが成長できるコミュニティを作る
代表的な人物には、現場第一主義、お客さまへの奉仕を第一に考え、お客さまに接する店頭のスタッフを支えるべき存在として上層組織を位置付けた、資生堂の元社長 池田 守男氏が挙げられます。
【リーダーシップ研修 関連セミナー】
・経営幹部に期待される役割と実務・行動力(柳瀬 智雄 氏)
・管理職・リーダーのためのリーダーシップ力養成と人に任せる技術(北村 信貴子 氏)
・リーダーシップと人材マネジメント(小杉 俊哉 氏)
・信頼を築いて人を動かすリーダーシップ(小倉 広 氏)
・リーダーシップと戦略の実行(梅本 龍夫 氏)
・管理職 リーダーシップ入門【午前】(鈴木 健一 氏)
・管理職 リーダーシップ入門【午前】(望月 禎彦 氏)
・管理職に必要な人材・組織マネジメント(山田 智大 氏)
・パーパスを実現する「両利きの経営」(梅本 龍夫 氏)
関連記事
【本ページをご覧の方は、以下のページもご参考にされています】